本文
令和元年度食育コラム
第3次奈良市食育推進計画に基づき、市民の食育への関心や理解を高めることを目的に、しみんだよりに食育コラムを掲載しています(平成29年4月~)。コラムは、奈良市食育ネット参加団体や市の関係部署が担当します。
令和元年度食育コラム
3月 弁当の日なら~食べることは生きること~子どもたちの未来のために

「弁当の日なら」で調理をする子どもたちの様子
奈良大宮ロータリークラブでは、子どもたちが自分で調理する体験を通じて、食への感謝の気持ちを深め、食事を自ら作る実践力を身につけ生きる力を育む「弁当の日なら」を実施しています。
この事業は、第3次奈良市食育推進計画の中でも、奈良県産食材の地産地消や食文化の継承にもつながる食育事業として位置付けられており、今年度は、令和元年10月にならファミリーで開催しました。
小学3~6年の子どもたちが奈良産のお米を使ったおにぎりや卵焼き、大和肉鶏のホイル焼き等4品を作りました。子どもたちからは「自分でにぎったおにぎりが美味しかった、家で家族に作ってあげたい」、保護者からは「家でお手伝いを楽しんでしてくれるようになった。後日、自ら夕食を作ってくれて感動した」等の嬉しい声がありました。
(奈良大宮ロータリークラブ)
2月 百貨店から奈良の魅力を発信!

大和路新発見展で大学生が地産地消お弁当を販売
近鉄百貨店奈良店では、地下1階「大和路ショップ」、5階「大和路暮らしの間」を中心に奈良の新たな魅力を生み出し、発信するプロジェクトを進めており、奈良県物産店「大和路新発見展」を年2回開催しています。
令和元年10月の大和路新発見展は奈良市食育ネットや奈良大宮ロータリークラブの協力で地域の子ども達に奈良の食に関心を持ち体験できる親子参加型イベントと同時開催し、沢山の方々にご参加いただきました。
また、平成31年4月には、概ね0~3歳の児童とその保護者が子育てに関する相談や交流の場として無料で利用できる「つどいの広場”マザーリーフ”」を6階にオープンし、地域のコミュニティづくりも行っています。これからも奈良の魅力を発信していきますので、ぜひお越しください。(近鉄百貨店奈良店)
1月 正月の習わし、元旦の料理
 お屠蘇
お屠蘇
「お屠蘇」一年の邪気を払い歳を伸ばすという伝承の酒です。元旦には新春の祝いとして家族全員に屠蘇を注いで回り、注がれると盃を上げ、新年を寿ぎつつ口をつけます。
 お雑煮
お雑煮
「雑煮」正月三が日は雑煮をいただきます。各地で多種多様ですが西日本は丸餅、東日本は各餅で、煮るか焼くかどちらかの方法で供します。味付けは西日本では白味噌仕立て、東日本では澄まし仕立て等が多く見られます。
 お節料理
お節料理
「お節料理」日本のお節料理は重箱に詰めるのが一般的で、正式な段数は4段とされています。一の重は「口取り祝儀肴」で、数の子や田作り、黒豆、その年の干支や松竹梅を形どったものや紅白のもの等。
二の重は「家喜物(焼き物)」で、季節の魚介類の味噌漬けや、合わせタレに付けて焼いたもの、鶏肉等を焼き上げたもの等。三の重は「酢の物」で、酢でしめた魚や紅白なます等。与の重は「炊喜合せ(たき合せ)」で、海老や野菜等、色々な煮物。それぞれが縁起物で豊年や実り、長寿などの祈願が込められています。(奈良県日本調理技能士会 梅崎正利)
12月

南部公民館での調理実習の様子
生涯学習センター・公民館では、市民の食への関心を高めようと、年間約50の食に関する講座を開催しています。また、主催講座等を通じて食文化・食生活に関する自主グループを育成し、市民の継続的な学びの場を作っています。
食に関する講座は、子ども・親子・シニア・男性・女性など対象を細かく設定し、それぞれのニーズに合わせて実施しています。例えば、食を通して親子でふれあう講座や男性料理教室などです。独り暮らしの高齢者や子どもの孤食、生産者と市民をつなぐなど、現代の食をめぐる課題に取り組む講座もあります。また、料理実習室のある公民館では実際に調理をすることもできます。公民館の講座や自主グループの活動に、ぜひご参加ください。(奈良市生涯学習財団)
11月 市立学校での食に関する指導

「奈良の食文化再発見、麦縄を知ろう」授業の様子
奈良市には43校の小学校と21校の中学校があり、そのうち24校に、食育の中核を担う栄養教諭・学校栄養職員を配置しています。これまで、食育の生きた教材である“学校給食”を食事の手本として、食に関する指導を進めてきました。
また、平成28年度から市内全ての小学校1~4年生を対象に「食育プログラム」をスタートし、「健やかな心身の育成を図るために、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけること」、「食を通して郷土(奈良)のよさを知り、自分の生まれ育った地域を誇りに思う心を育成すること」の二つを主な指導目標として、食に関する指導を行っています。今後は更なる食育の推進に向けて、学校・家庭・地域と連携を深め、プログラムの充実と対象学年の拡大に取り組んでいきます。(奈良市立小学校栄養教諭)
10月 フレイルを予防して健康長寿を目指そう
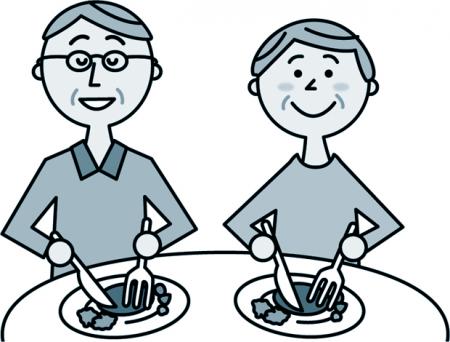
健康長寿のために大切なことは高齢期をおびやかすフレイルを予防することです。「フレイル(虚弱)」とは,、年齢にともない筋力や心身の活力が低下した状態をいいます。
特に高齢者は肉や魚や卵等の動物性たんぱく質を積極的に摂ることが大切です。たまに仲間と会食に出掛けたりするのも良いでしょう。新鮮な旬の食材を取り入れて美味しく、楽しい食卓にしましょう。(奈良県栄養士会奈良市支部)
9月 JAならけん女性大学の取組 新しい仲間との出会い・自分をスキルアップ
 女性大学”Na La shou-shou(ナ・ラ・シュシュ)”ロゴ
女性大学”Na La shou-shou(ナ・ラ・シュシュ)”ロゴ
 冬野菜の植え付け
冬野菜の植え付け
県内在住の若い世代の女性を対象としたJAならけん女性大学“Na La chou-chou(ナ・ラ・シュシュ)”を平成28年にスタートしました。これまで計256人が入学し、今年度は、第4期生71名が受講しています。食と農を中心に、生活に役立つさまざまなカリキュラムを通じて、自分磨きと地域の仲間づくりを楽しんでいます。
今年度の講座は、野菜ソムリエによる野菜の美味しい食べ方や選び方講座、冬野菜の植え付け・収穫体験、旬の食材を使った料理や郷土料理(柿の葉寿司)教室等で、5月には月ヶ瀬で茶摘み体験を行い、大和茶の魅力を体感することができ好評でした。今後も、食と農の大切さを発信し、地域の女性が楽しく学び、仲間づくりができる場を提供していきます。
(JAならけん)
8月 大和伝統野菜「小しょうが」から生まれたご当地ソフトクリーム

小しょうが

生産者の稲野さんと「株式会社粟」代表の三浦さん
大和伝統野菜とは、地域の歴史や文化を受け継いだ独特の栽培方法により「味、香り、形態、来歴」等に特徴を持つ野菜のことで、現在20品目あり、奈良市五ケ谷地区でも大和伝統野菜である「小しょうが」を栽培しています。
このしょうがでつくる「ジンジャーシロップ」を使ったご当地ソフトクリームは、生産者と近畿大学農学部、そして企業との共同開発により生まれたもので、爽やかな甘さの中にショウガの辛味がスッキリと広がる味が大人気。このソフトクリームを通じて、奈良市に古くから良質なしょうがの生産地があったことを知ってもらうきっかけになればと思います。
このソフトクリームは、ならまちセンター1階のレストランcoto coto(コトコト)で食べることができますので、今年の夏にぜひ味わってください。
(株式会社 粟)
7月 「持続農業法」に基づくエコファーマーの取組

県知事の認定を受けたエコファーマーは奈良県に375人、うち奈良市に62人(平成30年3月現在)
エコファーマーとは、環境にやさしい農業に取り組んでいる農業者の愛称で、(1)土づくりの技術(2)化学肥料を減らすための技術(3)化学合成農薬を減らすための技術の3つに取り組んでいます。大和高原野菜研究会では、エコファーマー認定作物で、化学肥料・化学合成農薬を3割以上低減した農産物に表示ができるシンボルマークも用いながら、消費者のみなさんにおいしくて環境にも優しい農産物をお届けしています。
(大和高原野菜研究会)
6月 奈良市の子ども食堂

子ども食堂の様子
奈良市ボランティアインフォメーションセンターには「子ども食堂」を運営する地域団体の登録があり、現在当センターが把握しているのは14か所(運営団体13)です。開催の頻度や、子どもも一緒に調理するか等、同じところは一つもありません。どこも当事者である子どもにとっては、「自分を大事に思ってくれる大人がいる」ことを感じられる場所です。「地域の大人が地域の子どもたちを真ん中に、食を通じた居場所をつくろうとしている」こと。そこから生まれる「つながり」を大事に思う人たちの手によって、少しずつ着実に広がっています。機会があれば、一度参加してみませんか。
(奈良市ボランティアインフォメーションセンター)
5月 大和情熱野菜とは

奈良県の農家さん自慢の野菜・果実を紹介するために食のプロが集う「奈良のうまいもの会」が2014年から取り組んでいる地産野菜ブランド化プロジェクトです。
奈良は日本で初めて都が置かれた「国のあけぼの」・「農のまほろば」。豊かな自然に育まれた奈良県の「大和伝統野菜」やナス、トマト、ホウレン草、柿、イチゴなど、驚くほど豊富な種類を誇ります。そのなかでも「大和情熱野菜」は、土壌管理などの生産基準をクリアした「情熱農家」が、品評会などを通して登録されます。これからも奈良が誇る野菜や果物をどんどん紹介していきたいですね。市民の皆さんからの推薦もお待ちしています。
(奈良のうまいもの会)
4月 第3次奈良市食育推進計画がスタートします

このたび作成した新しい推進計画では、食を通じて健康なからだと心を育み、みなさんが安心してくらせるまちを目指します。「食育」とは、生きる上の基本であって、知育・徳育・体育の基礎であり、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。米や茶など豊かな農作物に恵まれた奈良らしい食が受け継がれ、子ども達も、その未来の子ども達の命も輝きますように。子ども達が家庭で食に関わるお手伝いをすることが、食への関心を高め将来一人で生きていく力を身につけることにつながります。地域の食を通じたつながりや地元の食材を大切に、命や食環境を守り育て、未来につなぐことが今、私たち一人ひとりに求められています。
(農政課)
平成30年度食育コラム
目次
- 3月「ならの食育未来ワークショップ」 医療政策課
- 2月「食を通じて行事を楽しむ」 こども園推進課
- 1月「非常時にもあわてない!食と防災」 大阪ガス株式会社
- 12月「家庭の味を伝えよう。12月の行事食」 都祁保健センター管理栄養士
- 11月「奈良市学校給食 「古都ならの日」と「食育の日」 奈良市教育委員会保健給食課
- 10月「生・加熱不十分な鶏肉による食中毒にご注意」 生活衛生課
- 9月「奈良の米とその魅力」 奈良市4Hクラブ
- 8月いつまでもおいしく食べるために~オーラルフレイルとは~ 奈良県歯科衛生士会
- 7月つくる人と食べる人をつなぐ 「奈良食べる通信」の取り組み 株式会社エヌ・アイ・プランニング
- 6月「ロカボによる健康的な食生活を始めませんか」 株式会社ローソン
- 5月「ご存知ですか?HACCP(ハサップ)」 生活衛生課
- 4月「食からはじめる健康で豊かなまちづくり」 医療政策課
平成29年度食育コラム
目次
- 3月「消費・賞味期限の違いを知って、身近な食の循環を良くしよう」市民生活協同組合ならコープ
- 2月「クッキング保育について」 こども園推進課
- 1月「奈良市の学校給食」 奈良市教育委員会保健給食課
- 12月「宮廷料理と奈良の米食文化」 奈良市飲食店組合
- 11月「地域の食を通じた健康づくりをめざして」 奈良市食生活改善推進員協議会
- 10月「奈良の食文化の魅力」 NPO法人 奈良の食文化研究会
- 9月「食育(菜園活動)について」 こども園推進課
- 8月「夏休みも!早寝・早起き・朝ごはん」 健康増進課管理栄養士
- 7月「食中毒の予防について」 生活衛生課
- 4月「春はスタートの時期」 医療政策課
