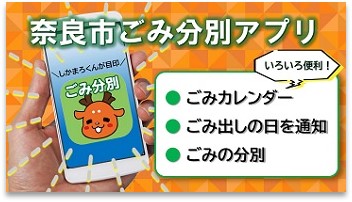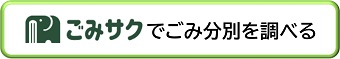本文
PCB廃棄物について
目次
- 各種届出の電子申請
- PCB廃棄物とはどのようなものか
- PCB特措法の制定について
- PCB廃棄物等の保管と所有に関する届出について
- 現在使用中のPCB使用機器について
- PCB廃棄物はどこでどのように処分すればよいのか
- PCB廃棄物の保管に関わる各種届出の様式
各種届出の電子申請
各種届出は、下記から行うことができます。
PCB廃棄物に関する届出フォーム<外部リンク>
届出書面に受付印が必要な場合、下記お問合せ先まで持参又はご郵送ください。
なお、持参又は郵送の場合は書面2部をご準備ください。
また、郵送の場合は必要分の切手を貼付した返送用封筒も同封してください。
PCB廃棄物とはどのようなものか
PCBは、Polychlorinated Biphenyls(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、工業的に合成された化合物のことです。このPCBは、水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、電気絶縁性が高い、不燃性であるなど物理的にも化学的にも非常に安定した性質を持っています。このため、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途に使われていました。

高圧トランス

高圧コンデンサ

安定器
非常に利便性の高い物質として様々な形で使用されたPCBですが、一方で脂肪に溶けやすく分離しにくい性質を持つことから、慢性的な摂取により人の健康を害することが報告されています。昭和43年にはカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化しました。また、PCBは食物連鎖などで生物の体内に濃縮しやすいこと、さらに環境中で分解されにくく長距離を移動して、地球規模での汚染(アザラシ、クジラ等への蓄積)を引き起こすことが報告されています。
このような有害性が明らかとなり、日本では昭和47年3月にその製造や新たな使用が一切禁止されています。
PCB特措法の制定について
PCBの製造や新たな使用は禁止されたものの、すでに製造されたPCBをどのように処分するのか、という課題は残りました。
このため、適切な処分を行うための処理施設設置の動きが過去に幾度かあったのですが、住民理解が得られないなどの理由で設置は実現せず、結果的にほぼ30年に渡ってほとんど未処分のまま保管が続くこととなりました。この長期の保管が続く中でPCB使用機器の紛失、不法投棄、破損による液漏れなどが起こり、環境への影響が懸念される状況となっています。
このような状況をふまえ、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が制定されました。この法律の主な内容として以下のようなことが上げられます。
「PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(以下、「PCB廃棄物等」という。)を保管あるいは所有している事業者は、令和9年3月31日(高濃度PCB廃棄物は奈良県内においては令和3年3月31日)までに当該PCB廃棄物等を適正に処分しなければならない。」
「PCB廃棄物等を保管あるいは所有している事業者は、保管状況等を管轄する行政庁(都道府県知事(政令市にあっては市長。以下同じ。))に毎年度届出しなければならない。」
「政府は、PCB廃棄物処理基本計画を策定しなければならない。また、地方公共団体(都道府県及び政令市)は基本計画に即して処理計画を策定しなければならない。」
「PCB使用製品製造業者は、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。」
この法律は、PCB廃棄物に関わるすべての者の責任を明確にし、適正処分までにタイムリミットを設けたことに大きな意義があります。
PCB廃棄物等の保管と所有に関する届出について
平成13年の「PCB特措法」の制定により、PCB廃棄物保管者には様々な規制が課されています。以下のことを必ず守ってください。
保管及び処分の状況の届出
PCB廃棄物等を保管あるいは所有している事業者は、毎年度6月末までに前年度の保管状況を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」に記入し、提出して下さい。なお、新たに保管あるいは所有が判明した場合も同届出書を提出して下さい。
〈届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます〉
高濃度PCB廃棄物を新たに保管することになった場合は、速やかに下記より調査票の提出をおこなってください。
【期間内の処分】
PCB廃棄物等を保管あるいは所有している者は、法律が施行された日(平成13年7月15日)から令和9年3月31日(高濃度は令和3年3月31日)までにPCB廃棄物等を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
なお、環境大臣又は都道府県知事は、この規定に違反があった場合、その保管者に対して期間を定めて必要な講ずべきことを命令できます。
〈この命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。〉
廃棄終了の届出
保管あるいは所有している全てのPCB廃棄物等を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託した日から20日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届書」を提出して下さい。
譲渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物等を譲り渡し、又は譲り受ける行為を原則禁止しています。但し処理技術の試験研究や処理施設における試運転を目的とする場合など、特例により許可される場合があります。(詳しくは当課までご連絡ください。)
〈この義務に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。〉
承継
保管者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その保管者の地位を承継するものとされています。保管者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を提出して下さい。
〈届出を行わなかった者、又虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられます。〉
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物等の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
〈この義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。〉
保管基準の遵守
PCB廃棄物等の保管については以下の点に注意してください。
- 保管場所に人が立ち入らないよう囲いを設け、明確な表示を行ってください。
- PCB廃棄物本体にも表示を行ってください。
- 万一の液漏れに備え、オイルパンを敷くか、容器を二重にするなどしてください。
- 保管場所に変更があった場合は、10日以内に移動前と移動後の保管場所を管轄する都道府県知事及び政令市長にその旨届け出てください。
- PCB廃棄物の保管に関わる各種届出の様式へ
現在使用中のPCB使用製品について
現在使用中のPCB使用製品については処分期間内に処分する必要がありますので、早急にPCBを使用しない製品と交換して下さい。また使用中であっても「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の届け出を行わなければなりません。PCB使用製品を所有されている方は《ポリ塩化ビフェニルの使用製品について》の記入欄に必要事項を記入し毎年6月末までに届出書の提出をして下さい。
現在使用中であっても処分期限は令和9年3月31日まで(高濃度の場合は令和3年3月31日)となりますので、このことを十分理解していただき機器入れ替え等の計画をして下さい。
PCB廃棄物はどこでどのように処分すればよいのか
PCB廃棄物は現在様々な規制の下、厳重な保管が義務づけられていますが、最終的にどこでどのように処分すればよいのでしょうか。
PCB廃棄物処分施設について
我が国における高濃度PCB廃棄物処分施設については、政府が100%の出資を行って平成16年4月に設立した「日本環境安全事業株式会社」(通称JESCO、旧環境事業団)が、同年12月に日本初となる高濃度PCB廃棄物処分業の許可を取得(北九州事業所分)しました。この法人の事業は全国を五つの区域に分け(北海道事業所・東京事業所・豊田事業所・大阪事業所・北九州事業所)、それぞれに処理施設を設置し、各区域に保管されている高濃度PCB廃棄物を順次処分していました。
奈良県内のJESCOでの対象事業所は、高濃度PCB廃棄物のうち3kg以下のトランス、コンデンサなどの電気製品、安定器などの処分は北九州事業所、3kg以上のトランス、コンデンサなどの電気製品は大阪事業所になっておりましたが、令和3年3月31日に処分期限を迎え、事業終了に伴って処分場は閉鎖となります。
したがって、今後処分先がなくなることから新たに発見された場合はその所有者等の責任において生活環境保全上の支障が生じないよう適切に保管し続ける必要があります。
高濃度PCB廃棄物をお持ちであることが判明した場合は、速やかに下記より調査票を提出してください。
また、PCB含有量が0.5~5000mg/kgの低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物)につきましては、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設又は微量PCB汚染廃電気機器等の処分業の許可を持つ事業者に処理を委託してください。こちらの期限は令和9年3月31日までとなります。
(環境省ホームページに処理事業者一覧が掲載されています。環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理>廃棄物処理の現状>ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物>廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について<外部リンク>)
(市内でPCB廃棄物の収集運搬が可能な業者につきましては、奈良県のホームページでご確認下さい。奈良県トップページ>県の組織>くらし創造部景観・環境局>廃棄物対策課>許可登録業者名簿>産業廃棄物処理許可業者一覧<外部リンク>>5.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない))
- 奈良県のホームページへ<外部リンク>
- JESCOホームページへ<外部リンク>
PCB廃棄物の保管に関わる各種届出の様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))記載要領[PDFファイル/40KB]
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))記載例[PDFファイル/27KB]
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
(様式第一号(一) [Excelファイル/65KB] / 様式第一号(一) [Wordファイル/32KB]) - ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管事業場の変更届出書
(様式第二号 [Excelファイル/32KB] / 様式第二号 [Wordファイル/47KB] / 記載要領PDFファイル/14KB) - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
(様式第四号 [Excelファイル/39KB] / 様式第四号 [Wordファイル/60KB] / 記載要領PDFファイル/15KB) - 承継届出書
(様式第七号 [Excelファイル/112KB] / 様式第七号 [Wordファイル/66KB] / 記載要領PDFファイル/19KB)
高濃度PCB廃棄物を新たに保管することになった場合は、速やかに下記手順書をご確認のうえで調査票の提出をおこなってください。