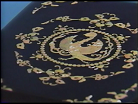本文
奈良漆器

わが国を代表する漆器工芸は、仏教伝来を契機とした天平文化とともに花開き、漆で絵を描いたもの、螺鈿(らでん)、金銀平脱、平文など多種多様な技法を自由に駆使して、目の覚めるような美しい器物を残しています。おそらく、直接器物を輸入すると同時に、工人を中国から招いて製作にあたらせ、日本人に伝習させたのでしょう。
そのころの数多くの作品が正倉院に収められているので、奈良は日本の漆器の発祥の地といわれています。
中世になって、塗師・漆屋座が登場します。南都に住んで社寺に所属し、建造物の塗師として活躍しながら器物としての漆器も制作していました。
また、茶の湯の発展とともに、茶道具関係の塗師に名人上手が現れ、江戸時代には武具の塗師を職業とする人もいました。
その後、明治に入って奈良博覧会会社が設立され、正倉院宝物や社寺の什器がはじめて公開された明治8年の第1回博覧会の開催によって奈良の漆工達は大いに啓発され、これらの模写事業を興して、工芸品としての奈良漆器の復興がはかられました。なかでも、螺鈿塗の技法は奈良の独壇場です。
↓制作の様子を動画でご覧いただけます。
奈良県ホームページ「奈良漆器」<外部リンク>