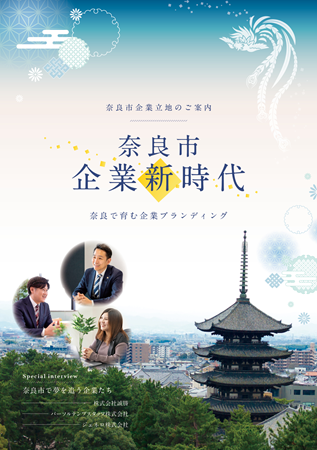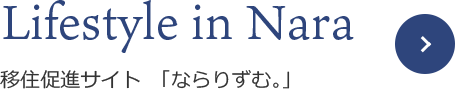本文
インタビュー(DMG森精機株式会社 アカデミー 部長 小林 龍一さん)
創業地の奈良で、未来に向けた多様な地域貢献を
日本を代表する工作機械メーカーとして、高度な技術とイノベーションを地域にもたらし、地元・奈良の経済発展と雇用創出に寄与しているDMG森精機。特に、2022年にJR奈良駅前に開設した「奈良商品開発センタ」は、地域の産業基盤を強化し、奈良市を先端技術のハブとして位置づけることに貢献しています。さらに注目すべきは、地元の教育機関との連携です。奈良女子大学とともに女性の研究者や技術者の育成に力を入れることで、地域の学術レベルを向上させ、奈良出身の才能が地域外に流出することなく、地域内で活躍するチャンスも提供しているのです。こうした育成プロジェクトに関わる小林龍一さんにお話を伺いながら、DMG森精機と奈良市の持続可能なパートナーシップに迫ります。

2022年に、JR奈良駅前に設立された奈良本社(「奈良商品開発センタ」)奈良県奈良市三条本町2-1)。
この拠点の稼働開始を機に、本社機能を愛知県名古屋市から奈良県奈良市へ移転。
東京都江東区の東京グローバルヘッドクォータとともに、二本社制を導入した
<プロフィール>
DMG森精機株式会社<外部リンク>
アカデミー部長 小林 龍一(こばやし りゅういち)さん
2017年 東北大学大学院工学研究科にて博士号取得。DMG森精機に入社後、加工技術開発、人事を経て現在はアカデミーにてデジタル /リアルの技術教育業務に従事。奈良女子大学工学部非常勤講師として、「先端設計生産工学概論」 をはじめとした3つの科目の授業・実習を担当している。
奈良オフィスの開設は、「万が一に備える」事業継続の強化
―――貴社は東京にグローバル本社を置き、世界に 116 の拠点をお持ちですが、2022年に奈良市に第二本社/「商品開発センタ」を開設された理由をお聞かせください。
小林さん:
 一つ目は「万が一に備える」事業継続の強化です。災害や疫病があっても、東京と奈良の本社が支え合い、サービス提供を一瞬たりとも止めない体制を整えました。二つ目は、JR奈良駅近くという好立地が、先端技術の開発拠点として「奈良商品開発センタ」を開設するにあたり、最適だと考えたからです。奈良へは、京都、大阪天王寺それぞれから電車で約30分とアクセスも良好。伊賀・奈良工場へは奈良オフィスからシャトル便が30分おきに出ており、時間を気にせずに移動できます。また奈良市周辺にさまざまな教育機関や、機械・電気系のメーカー、そこで働く社会人・シニア層が多数いるため、新卒に限らずリクルートの拠点としても機能します。加えて、奈良は創業地ですから、地域貢献という観点からも意義深い選択でした。
一つ目は「万が一に備える」事業継続の強化です。災害や疫病があっても、東京と奈良の本社が支え合い、サービス提供を一瞬たりとも止めない体制を整えました。二つ目は、JR奈良駅近くという好立地が、先端技術の開発拠点として「奈良商品開発センタ」を開設するにあたり、最適だと考えたからです。奈良へは、京都、大阪天王寺それぞれから電車で約30分とアクセスも良好。伊賀・奈良工場へは奈良オフィスからシャトル便が30分おきに出ており、時間を気にせずに移動できます。また奈良市周辺にさまざまな教育機関や、機械・電気系のメーカー、そこで働く社会人・シニア層が多数いるため、新卒に限らずリクルートの拠点としても機能します。加えて、奈良は創業地ですから、地域貢献という観点からも意義深い選択でした。
旧国道24号線沿いの事業所周辺を、奈良を代表する美しい地域に
―――奈良市を拠点とした、今後の事業プランや御社ならではの取り組みについて、具体的に教えてください。
小林さん:
弊社ではサスティナビリティの観点から、2021年12月より奈良事業所周辺(旧24号線沿線)の景観美化計画を進めていますが、桜を約100本植樹する緑地化計画に加え、舗装工事や街灯の設置なども行っています。加えて、JR奈良駅から郡山ICまでの約5〜6kmの範囲に、子会社である株式会社マグネスケールのBCP対策として、レーザースケールの生産工場を建設する計画が進行中で、この周辺に弊社が数棟の建物を建設することにより、旧国道24号線沿いを、奈良を代表する最先端産業の集積地にしたいと考えています。
古都奈良との調和を目指したオフィスを新たな拠点として
―――隈研吾氏が手掛けた「奈良商品開発センタ」は建築デザイン的にも大変印象的ですが、どのようなコンセプトで計画が進んだのでしょうか。
 「奈良商品開発センタ」は6階建てで、 1階が機械開発、2階が要素技術開発、3~5階はオフィスフロア、6階がカンファレンスセンタ、レストラン、カフェとなっています。1階ホールの内壁に使用されている木目パネルは、隈研吾建築都市設計事務所にデザイン監修とモデルデータ作成を依頼し、株式会社Aiソリューションズによる加工プログラム作成、加えて62社のお客様の協力を得て自社製の工作機械を用いてアルミ板を切削し加工されたものです。ヒューマンスケールで温かみのあるオフィスで、“古都奈良と調和する建築”をコンセプトとしています。
「奈良商品開発センタ」は6階建てで、 1階が機械開発、2階が要素技術開発、3~5階はオフィスフロア、6階がカンファレンスセンタ、レストラン、カフェとなっています。1階ホールの内壁に使用されている木目パネルは、隈研吾建築都市設計事務所にデザイン監修とモデルデータ作成を依頼し、株式会社Aiソリューションズによる加工プログラム作成、加えて62社のお客様の協力を得て自社製の工作機械を用いてアルミ板を切削し加工されたものです。ヒューマンスケールで温かみのあるオフィスで、“古都奈良と調和する建築”をコンセプトとしています。
※関連動画 https://www.dmgmori.co.jp/movie_library/movie/id=6359<外部リンク>
工学において卓越した女性研究者・技術者の育成のために
―――2022 年に奈良女子大学と包括連携協定を結び、理工学系の女性研究者や技術者の育成などで連携を図っていますが、具体的な取り組みの内容と手応えをお聞かせください。

小林さん:
奈良女子大学と弊社は以前から女性研究者・技術者の育成の在り方について議論を行っており、具体的な取り組みは2022年4月、工学部の新設を機に開始しました。工学において卓越した女性研究者・技術者の育成のためには専門知識に加え、社会問題や製造業に対する興味や理解、工学研究を実践するための実践的な設計、試作、評価能力が必要です。弊社は学生の能力を養うため、昨年まで工学部に一つの座学授業、一つの実習授業を提供しており、実習授業においては弊社の「奈良商品開発センタ」で最新の工作機械「NTX 500」を用いた実習を行っています。同授業では比較的自由な形式のレポートをテーマに、学生が多様な興味、強い探求心を発揮して課題にチャレンジし、さらには大学生に健全に働きながら社会や技術について学ぶ機会を提供するべく、1年間以上を想定した長期インターンシップを実施しています。また、将来を担う中高生に対するアウトリーチも重要だと考え、同施設を用いた全国の中高生へのワークショップも開催しています。
奈良から世界へ、将来へ向けての大きな飛躍を
―――工学系の若い才能を育む場所として、奈良市のポテンシャルについてはどのような印象をお持ちでしょうか。
小林さん:
総じて感じるのは、工学研究者・技術者としての機械・製造業への接点への重要性です。学生は授業やワークショップ、インターンシップを進めることで、本来であれば身近にある機械、製品、ものづくりへの理解を深め、社会に対する興味や将来のキャリアへの前向きな姿勢を獲得することができています。奈良市は豊かな文化や歴史、伝統産業、自然を有しており、海外からの関心が高い土地でもあります。これからグローバルに活躍していくためには、技術について学ぶこととともに、日本について学ぶことも極めて重要になりますが、奈良はそのためにとても素晴らしい場所です。奈良女子大学は真剣に学びに取り組む学生が多いですから、彼女らが実社会への興味、海外への興味、そして日本の文化・歴史への理解を深めていくことで、将来へ向けて大きな飛躍をしていくものと信じています。
<取材後記>
今回の話を通じて印象深かったのは、奈良市において教育と産業が密接に連携し、相乗効果が生まれているという点です。特に、DMG森精機と奈良女子大学がともに取り組む実践的な技術教育は、学生に実際の製造業界の空気を感じさせ、彼女たちが将来社会に出たときの糧となるでしょう。また、中高生へのアウトリーチ活動を通じて、より幅広い世代に機械や製造業への関心を持ってもらうことも目指しています。このように、奈良の豊かな文化的背景と教育への真摯な姿勢を活かし、地元だけでなく国際的な舞台で活躍する技術者を育てるための基盤が、日々着々と築かれているのです。
記事作成日:令和6年3月
記事作成:世界文化社