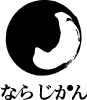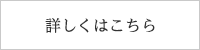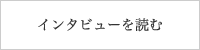日本酒を味わう時間
日本酒を味わう時間
2013年、和食が無形文化遺産に登録されて以降、和食と併せて世界的に注目が高まってきている「日本酒」。 国酒として古くから神に供えられ、祝いや喜びの席では欠かせなかった、まさに神聖な日本の文化ともいえるもの。 実は、この日本清酒の発祥の地といわれているのが奈良なのです。 古都・奈良には多くの大寺院が集中し、荘園でつくられた米で「僧坊酒」なるものが造られていました。 これこそが、現在の卓越した酒製造技術へと繋がる第一歩だったのです。 米の旨みを生かした上品な味わいの清酒のルーツに想いをはせながら、旨し奈良酒を飲んでみませんか。
人々が紡ぐ「現代の南都諸白」
奈良時間の中で味わう物語
「清酒発祥の地」として、約600年前に近代醸造の基本となる酒造技術醸造技術を確立した正暦寺。現在日本の寺院で酒母(酛)の製造免許を持ち、許可されているのは、この正暦寺ただ一寺です。その酒母は「菩提酛(ぼだいもと)」と呼ばれ、一度は長い歴史の中で作られなくなってしまいました。
かつて高級酒の代名詞として使われた「奈良酒」。歴史とともに作られなくなった、600年前の酒母「菩提酛(ぼだいもと)」。この「菩提酛」を奇跡的に復活させた物語が、奈良にはあります。
この奈良の日本酒にまつわる数々の物語を伝え、国内はもとより海外の方の心をも動かし、多くの方に味わい、楽しんでいただく。それが「奈良の日本酒」の目指す姿です。
 正暦寺 住職 大原弘信さん
正暦寺 住職 大原弘信さん
奈良の日本酒の特徴
| 水 | 春日原生林、吉野・生駒山系の伏流水等の清らかな水を使用。 |
|---|---|
| 米 | 大和平野、高原の上質米を使用し、飲みやすく、さわやかなすっきりとした味わいに。 |
| 酵母 | それぞれの蔵がこだわりの酵母を使用。また、正暦寺の菩提酛を使った酒が現存。 |